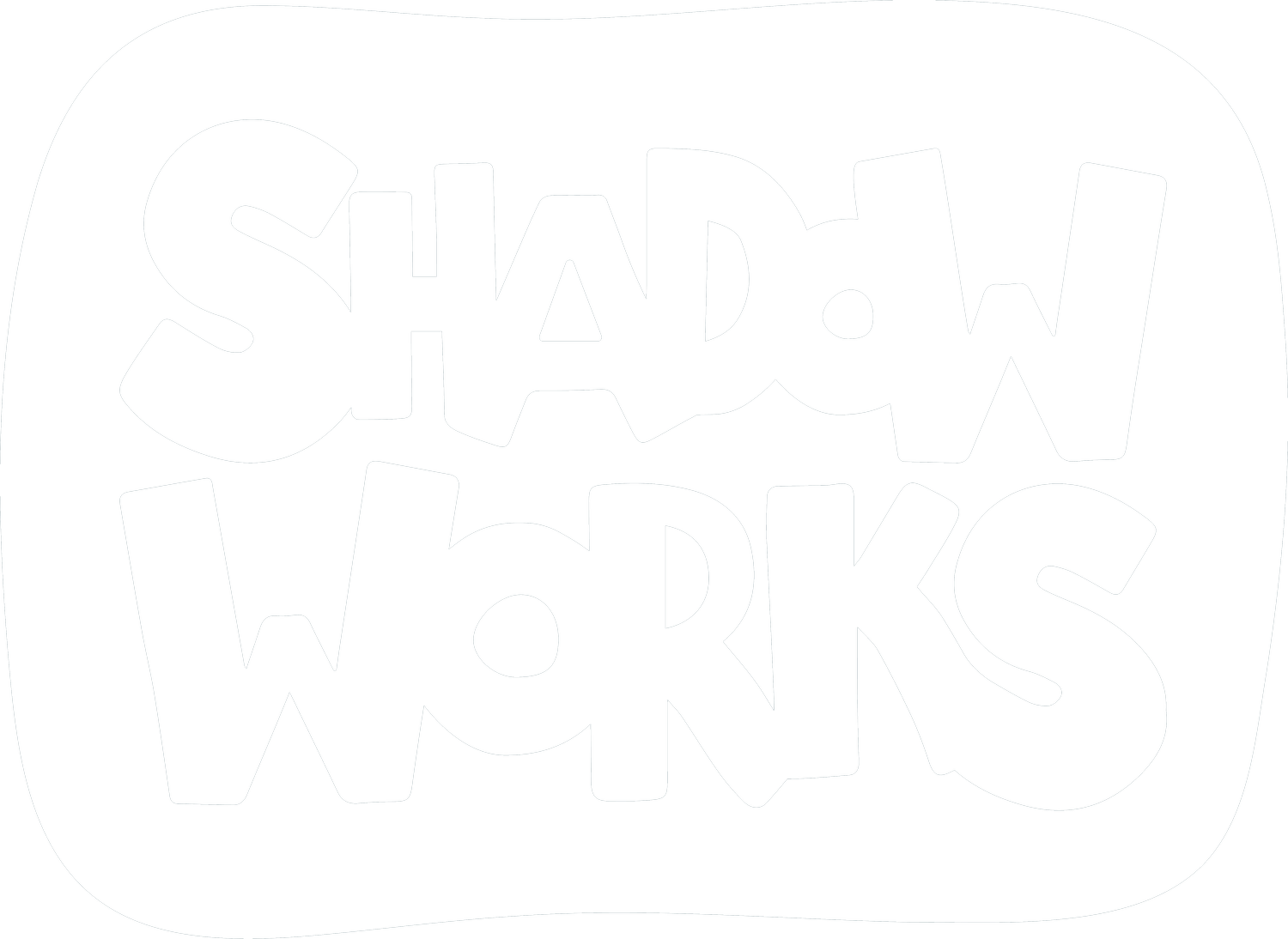禪 の 一 問
一
私の友人はうすい黃色の書物を開いたが、一見この佛書の版木師の忍耐の分る驚くべき文字である。漢字の活版は甚だ便利であらうが、こんな古い木版の美しさに比べると、どんなによくできた物でも、醜その物である。
『珍らしい話があります』
『日本の話ですか』
『いえ、――支那の話』
『何と云ふ書物ですか』
『その書物の名を日本風に私共は「無門關」と讀んでゐます。禪宗で特別に硏究される書物のうちの一册です。禪宗の或書物の特色の一つは、――これがよい例ですが――說明のない事です。ただ暗示を與へるだけです。質問が出て居るが、その答は硏究者が自分で考へ出さねばならない。答へへを考へ出さねばならないが、それを書いてはならない。御承知の通り、禪は言外に思想の到達すべき人間の努力を表はして居る物です、それで一たび言語と云ふ狹い物になつて現れたら、禪の特色を失ひます。……さて、この話は本當の話となつて居るのですが、ただ禪の一問としてここに使はれてゐます。この支那の話が三通(とほ)りに違つてゐますが、私はその三つの正味を申しませう』
つぎのやうに友人は話した、
譚者註 「類說離魂記」「剪燈新話」等、少しづつ話が違つて居る。たとへぱ蜀にゐた年數、子女の歌など小さい點に於て。
[やぶちゃん注:「類說離魂記」実は実在しない書物である。後注参照。★なお、「離魂記」を全く知らない方は、以下は本篇の肝心な部分のネタバレになるので、飛ばして小泉八雲の本文だけを読まれたい★。
「剪燈新話」明代に書かれた志怪小説集。撰者は瞿佑(くゆう)。特に怪談「牡丹燈籠」の濫觴である「牡丹燈記」で知られる。同書の「金鳳釵記」(きんほうさいき:鳳凰を象った簪(かんざし)の物語)は、そのモチーフと展開が「離魂記」とよく似ており、創作の原拠の一つとしたことは確かであろうが、同じ話ではない(原話は一人の女性の霊魂の離脱であるが、「金鳳釵記」では姉妹二人を絡ませてある)。
さても何故、このような誤認を小泉八雲や訳者田部隆次氏がしてしまったかと言うに、彼らにその責任があるわけでは実は全くなく、永くこの存在しない「類説離魂記」や、「剪燈新話」に恰も「離魂記」がそのままに所収されているかのように「無門関」の通俗注釈書等に書き継がれてきてしまった事実に依拠するのである。これについては、松村恒氏の論文「『無門関』第三十五則「倩女離魂」の材源について」(『印度學佛教學研究』第四十七巻第二号・平成一一(一九九九)年三月発行。こちらからPDFでダウン・ロード可能)が非常に詳しいので参照されたいが、冒頭で松村氏は、まさに小泉八雲の本篇の田部氏のこの「註」について以下のように語っておられるのである。
《引用開始》
事の発端はこうであった。小泉八雲の禅問答の紹介の一文「禅書の問」(『異国情趣と回顧』所収) に、『無門関』第三十五則に関わる倩女離魂の物語とその解釈が例として挙げられている。この一文の初訳である田部隆次訳は注にて「『類説離魂記』『勇燈新話』等」、と解説を付けるのであるが、不明瞭であった。ただこの不明瞭さについては、八雲の邦訳者ばかりを責めてはいられない。『無門関』の通俗的解説書もまた同様であったからである。
《引用終了》
として、トンデモない事実が明かされてゆくのである。以下は松村氏の論文を熟読されたい。]
二
『類說離魂記』に記され、『正燈錄』に物語られ、禪宗の書物である『無門關』に批評されて居る倩女の話、――
[やぶちゃん注:「正燈錄」「宗門正灯録」(しゅうもんしょうとうろく)東陽英朝著・愚堂東寔編。唐の南嶽禅師以下の臨済宗の歴代正脈二十三祖の列伝。漢文体記載。近世初期の成立。]
衡陽[やぶちゃん注:「こうやう(こうよう)」。]に張鑑と云ふ人がゐた、その人の小さい娘の倩[やぶちゃん注:「せん」。]は非常に美しかつた。王宙と云ふ甥もゐたが――それも立派な少年であつた。この二人は一緖に遊んで、仲が良かつた。一度鑑は戲れに甥に云つた、――『いつかお前を私の娘に見合せるつもりだ』二人の子供はこの言葉を覺えてゐた、そして彼等は言名付[やぶちゃん注:「いひなづけ」。]になつたと信じてゐた。
[やぶちゃん注:原作では時は則天武后の「天授三年」(西暦六九二年)とする。
「衡陽」現在の湖南省衡陽県(グーグル・マップ・データ。同じ以下)。なお、原文では地名や姓名を中国音で示しているが、一部は少なくとも現代中国語音としては納得出来ない表記である(しかし煩瑣なのでそれは問題にしない)。
「張鑑」原作では「張鎰(ちやういつ(ちょういつ))」である。原文“Chang-Kien”。
「倩」本字には「美しい」・「口もとが愛らしい」の意がある。原文“Ts’ing”。
「王宙」原文“Wang-Chau”。]
倩が大きくなつた時、或位の高い人が彼女を娶らうとした、彼女の父はその要求に應ずる事に決した。倩はこの決心によつて非常に煩悶した。宙の方では[やぶちゃん注:ここ底本は「宙」は「張」となっているが、「宙」の田部氏の訳の誤りであることは明白である。原文“As for Chau, he was so much angered and grieved that he resolved to leave home, and go to another province.”であるからして、特異的に訂した。]、餘りに怒りかつ悲んで、家を捨てて他の州に行く事を決心した。その翌日彼は旅行のために船を用意して置いて、日沒の投誰にも別れを告げないで河を溯つた。ところが夜中に彼は自分を呼ぶ聲によつて驚かされた、『待つて下さい――私です』――そして彼は船の方へ、岸に沿うて走つて來る一人の少女を見た。それは倩であつた。宙[やぶちゃん注:同じく底本は「張」で誤訳。出すまでもないが原文は“Chau was unspeakably delighted.”であるから、特異的に訂した。]はこの上もなく喜んだ。彼女は船に跳び乘つた、それからこの二人の愛人は蜀の國に安全に着いた。
蜀の國で彼等は幸福に六年暮らした、二人の子供をもつた。しかし倩は兩親を忘れる事はできなかつた、そして再び兩親を見たいと度々思つた。たうとう彼女は夫に云つた、――『以前私はあなたとの約束を破る事ができなかつたから、―――私は兩親にあらゆる義務と愛情を負うて居る事を知りながら、――あなたと驅落をして兩親を見捨てました。もう兩親の赦しを願ふやうにする方がよくないでせうか』『心配せんでも宜しい』宙[やぶちゃん注:同前で底本は「張」。特異的に訂した。]は云つた、――『今度は遇ひに行かう』彼は船を用意した、それから數日後に妻をつれて衡陽に歸つた。
こんな場合の習慣に隨つて、夫は妻を船に殘したままで先づ鑑の家に赴いた。鑑は如何にも嬉しさうに甥を歡迎して云つた、――
『どれ程これまでお前に遇ひたかつたらう。どうかしたのだらうとこれまでよく心配してゐた』
宙は恭しく答へた、――
『御親切な言葉をうける資格はありませんで、恐縮です。實は私が參りましたのは御赦しを願ふためです』
しかし鑑にはこれが分らなかつたらしい。彼は尋ねた、――
『お前の云ふ事は何の事だらう』
『實は倩と逃げて行つた事で、怒つていらつしやると思つて心配しました。私は蜀の國へ連れて行つたのですから』
『それはどこの倩だらう』鑑は尋ねた。
『お孃さんの倩です』宙は答へ方が、自分の舅に何か惡意のある計畫でもあるのではないかと疑つて來た。
『お前は何を云つて居るのだ』鑑は如何にも驚いたやうに叫んだ。『娘の倩はあれからずつと病氣だ、お前が出て行つてからこの方』
『あなたのを孃さんは病氣ぢやありません』宙は怒つて答へた、『六年間私の妻になつてゐます、それから子供が二人あります、それで御赦しを願ふために二人でここへ歸つて來たのです。それですからどうか嘲弄する事は止めて下さい』
暫らく二人は默つて顏を見合せてゐた。それから鑑は立つて、甥について來るやうに手招きをしながら病人の少女の寢て居る奥の一室に案内した。そこで非常に驚いた事には、宙は倩の顏、――綺麗だが、妙にやせて蒼白い倩の顏を見た。
『自分では口を利く事はできないが、話は分る』老人は說明した。それから鑑は娘に笑ひながら云つた、『宙さんの話ではお前は宙さんと驅落ちして、今では二人の子もちださうだ』
病人の娘は宙を見て微笑した、しかし何も云はなかつた。
『今度は私と一緖に河へ來て下さい』途方にくれた婿は舅に云つた。『私はこの家で何を見たにしでも、――お孃さんの倩は今丁度私の船の中に居る事は保證して云ふ事ができます』
彼等は河へ行つた、そして實際そこには若い妻が待つてゐた。そして父を見で。娘はその前に低頭して容赦を願うた。
鑑は彼女に云つた、――
『お前が本當に私の娘なら、私はお前を愛するばかりだが、どうも娘らしくも思はれながら、分らない事がある。……一緖にうちへ來て貰ひたい』
そこで三人は家の方へ進んだ。そこに近づくと、その病人の娘、――長い間床を離れた事のない娘、――は太層嬉しさうに微笑しながら、三人を迎ひに來るところであつた。そこで二人の倩は互に近づいた。ところがその時――どうしてだか誰にも分らないが――彼等は不意に互に融け合つた、そして一體、一人、一倩となつて、前よりも一層綺麗になつて、病氣や悲哀の何のしるしも殘つてゐなかつた。
鑑は宙に云つた、――
『お前が行つてからこの方、娘は啞になつた、そして大槪は酒を飮み過ぎた人のやうであつた。今考へると魂が留守になつてゐたのであつた』
倩自身も云つた、
『實は私はうちにゐた事は知りませんでした。私は宙が怒つて默つて出て行つたのを見ました、そしてその晚船のあとを追かけて行つた夢を見ました、……しかし今となつてはどちらが本當の私であるのか、――船に乖つて行つた私か、それともうちに殘つてゐた私か、――分りません』